「東京三大居酒屋」の名店が秋田「両関」だけを扱う理由

上野不忍池の近く、湯島の繁華街をはずれた辺りの路地に、大きな杉玉が目印の「シンスケ」という居酒屋があります。からっと表の引き戸をあけて入り、右にあるもう一つの中の引き戸をくぐると、檜板のすーっと通ったカウンター席がまっすぐ続いています。二階のイス席ではそれぞれ数名でワイワイと盛り上がっていますが、一階は基本的に二人くらいで機嫌良く、あるいは一人で反省をしながらしっとりと飲む場所です。
ここは東京三大居酒屋に一つに数えられ、はたまた「西の金田、東のシンスケ」とも言われる名酒場。角の立った新鮮な刺身、コクと旨味がぎゅっと詰まった絶品の鮭の焼き漬け、ホッとするメンチカツなど美味しい肴たちももちろんですが、大正年間以来の伝統とお店の方々のピッとした所作が作り出す独特の重厚な雰囲気が、名店の所以です。
また、酒場ですから、お酒が大事です。こだわっております。1階では生ビールはなく、瓶ビール、しかもサッポロの赤星のみ。数えて七代目の若旦那が「スポーン」と気持ちよく開けてくださいます。
かるくツマみながらビールを流し込んだあと、そして、ここからが本題のお酒(日本酒)です。居酒屋といえば日本酒の品揃えを競い合っているものだと勝手に思っていますが、さらりと言われます。「うちは両関のみです。」
どうしてそうなのか、尋ねてみました。
「『くだらない』っていう言葉ありますよね。」
はい、ありますね。
「あれ、日本酒と関係があるんです。昔、お酒といえば灘の酒が一流。ほかは二流とされていました。灘の酒は上方から江戸へ下ってくるので『下り酒』と呼ばれていて、これ以外の酒が『くだらない』酒だったわけです。また、当時は海運で運ばれたんですけど、この船の揺れ具合がお酒を慣らすのに良かったようですね。上方の人もわざわざ船で東まで運んで西に戻してから飲んだと言われます。これを『富士見酒』と呼んだそうです。」
はーなるほど。昔の人も七代目の語り口も”粋”そのもの。
「この下り酒一辺倒に早くから切り込んだのが秋田の両関さんなんです。寒冷地の秋田で蔵を二重にするなど早くから技術を磨き、東京でも評判が良くなってきました。十四代、八海山や他の寒冷地の造り酒屋にも両関さんの技術が伝わっているようです。うちはもともと酒屋をやっていたので両関をはじめ、いろいろなお酒を扱っていたのですが、戦後の混乱期にいろいろ両関さんには本当にお世話になって、それからお酒は両関のみになりました。」
義理と人情を酌み交わす酒場だからこそ、こういうことを大事にされているんですね。
とろっとした旨味の奥に、ほんの少しの酸味と、樽の風味のほろ苦さも抱いた、ひや(常温)の両関をこくっと呑みながら、自分の仕事もこういう魂を込めてやっているかなぁと、亡くなった先代の社長に「くだらねえことやってんじゃねえよ」と言われないか、しっとりと考えるのでした。

;)





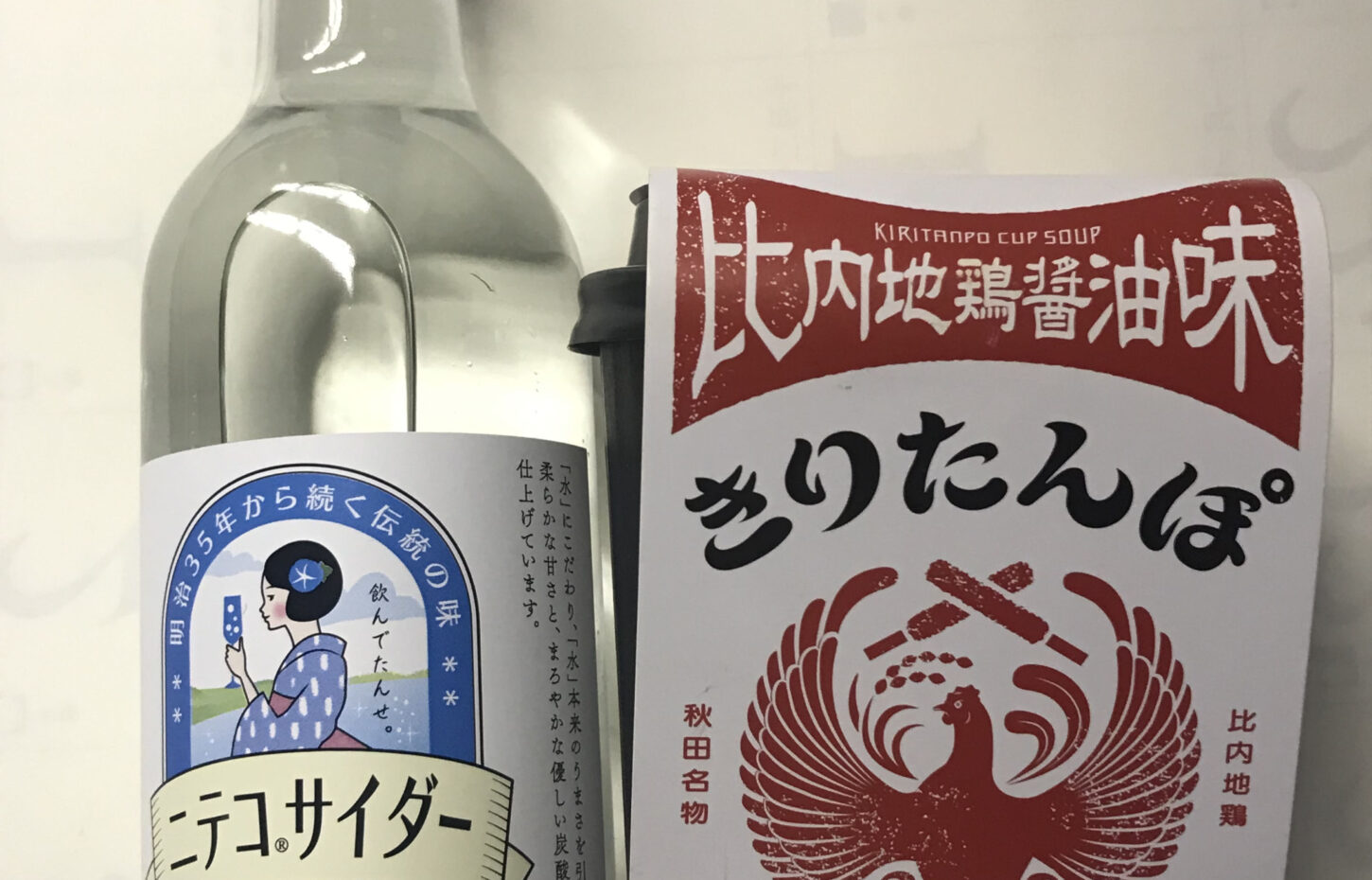


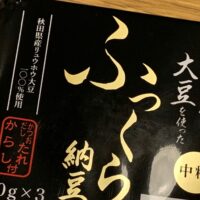
この記事へのコメントはありません。