比内鶏の比内はアイヌ語

どうも、週いち秋田記者のまいちゃんです。どうぞお見知りおきのほどよろしくおねがいします。
さてみなさま、「比内鶏」ご存知ですか?
「比内鶏」は天然記念物で食べられませんが、そこから交配した「比内地鶏」は食べられます。言わずとしれた日本三大地鶏の一つで、秋田名物の筆頭ともいえますね。
で、この「比内」というのは秋田の北部の地域の名前なんですが、Wikipediaによると「郡名の語源はアイヌ語の「ピ・ナイ」(小石が多い沢)、または「ピン・ナイ」(細く深い谷川)からきているといわれる」ということで、なんとアイヌ語が語源なんですね。言われてみれば北海道の「稚内」など、「内」がつく地名と共通してます。
秋田には他にも「板見内(いたみない)」「毛馬内(けまない)」「桧木内(ひのきない)」などもあり、中には「笑内(おかしない)」という関西の芸人が聞いたら嫌がりそうな地名もあります。
他にも青森、岩手などとともに、北東北を中心にアイヌ語を語源とした地名があります。気仙沼の気仙や、十和田湖の十和田などもそのようです。
いうまでもなく、古代日本においてこの地域にいた蝦夷(えみし)の名残といえます。鎌倉幕府が奥州藤原氏を滅亡させ東北すべてを支配下に置くまでは、異文化の人々の国であったわけです。
Wikipediaには「エミシは、当時の東北人から鬼と呼ばれていたらしい」ともあります。どうにもなまはげを連想させますね。さらに、山間に暮らし狩猟を主に行っていた「マタギ」は、山ではあえて里の言葉を使わず、アイヌ語に通じる「マタギ言葉」を使っていたとのこと。
異文化同士ただ融合するのではなく、なんとなく違いを持って同居をしている。なまはげのような「来訪神」を祀る文化が続いている。弥生文化と縄文文化、大和人とエミシ、里で暮らす人々とマタギ、暮らしの中にやってくるなまはげ。中央集権による画一化がおよびにくい地域だからこそ、日本古来大切にしていたであろう「違いを敬い、出会いを大切にする文化」が残っているのかもしれませんね。
考えてみれば比内地鶏は秋田固有種の比内鶏と、ロードアイランドレッドという外来種の掛け合わせでできています。そういうことを考えながら食べると、また深く味わえるような感じもしますね。


;)
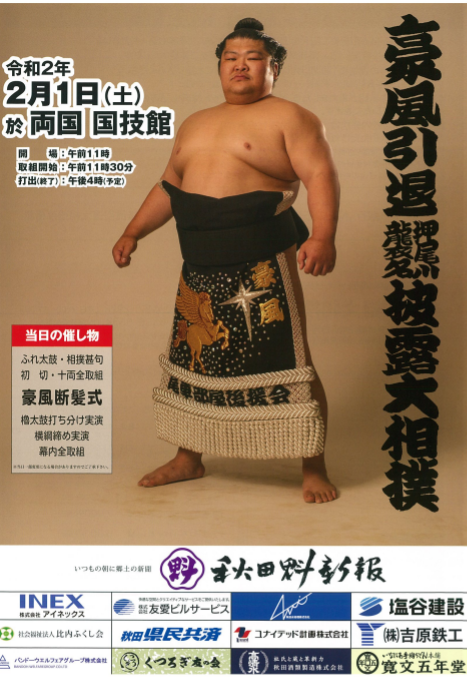







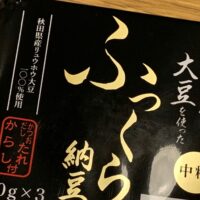
この記事へのコメントはありません。